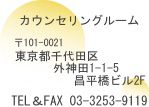 |
2006年9月 Vol.33 「消費者力」NPO法人女性自立の会 理事長 有田宏美 9月8日金曜日、読売新聞夕刊に、当会の活動が紹介され、その日の夕方からは、相談の電話がひっきりなしに続きました。相談内容は、多重債務問題に限らず、消費生活一般に関わるものも多く寄せられました。 前会報で、当会で行っている再生プログラムや、企業の新人研修で行った「消費者力クイズ」の話を書きましたが、今回の新聞掲載後の相談でも、自分を守るための知識の乏しさ、間違った知識への思い込みに捕らわれている人の多さに驚きと同時に危機感さえ感じました。最近でも、振り込め詐欺の問題や、「モデルにならないか」と誘い、宝石を買わせる悪質商法の被害が大きなニュースになっていましたが、多重債務への入り口は、騙されていることに気がつかない小さな心の油断と知識の乏しさから始まる場合が多いのです。 先日、以前相談に見えられた方から、「最終警告と書かれた葉書が届いた」と、うわずった声で連絡を受けました。知っている者からすれば、それが、悪質な架空請求であるとわかっていても、相談者にとっては、後ろめたさゆえの不安があり、戸惑いと、身内や周りに知られたくないという思いから、冷静な判断力を失ってしまうようです。 また、カウンセリングをしていると、「人からの評価」と「自分の価値観」のバランスを崩している人が多いことに気がつきます。彼女たちは、人の自分に対する評価や、相手の気持ちばかりを気にして、相手の気持ちを先読みしてしまいます。 読売新聞の記事を見て相談に見えられた方は、「同僚に、お金を貸してほしいと頼まれ、最初は、断ったものの、度重なる要求に断りきれず、金融業者2社より借り入れ、同僚にお金を渡した。ところが、数ヵ月後、同僚が仕事をやめて連絡が取れなくなってしまい、私には借金だけが残った」と話してくださいました。 彼女の心の中にも、断ることへの気まずさ、同僚に嫌われたくない、同僚との関係を崩したくないという思いがありました。人は完璧ではありません。万人に好かれる人もいなければ、万人に嫌われる人もいないのです。人の気持ちや評価ばかり捕らわれた生き方は、知らず知らずのうちに、自分で自分を苦しめる結果となってしまいます。だからこそ、これからの消費社会を生き抜くために、周りに流されることのない、一人ひとりの消費者力を養うための消費者教育が必要だと痛感するこの頃です。
|
||||||||||||||||||||||||||